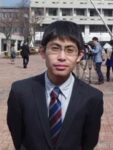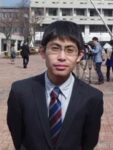皆さん、こんにちは。台湾・台中市の静宜大学というところで日本語を教えている、古賀悠太郎と申します。
今回は、日本語の「の」についてお話しします。中国語話者に日本語を教えたことがある方、あるいは中国語話者と日本語で話したことがある方ならば、「*高いの山」のような〈「の」の使いすぎ〉は印象的だと感じることの一つではないでしょうか。そして、これとは反対に、「*日本では現地文化に驚きました」(→現地の文化)のように〈「の」の不足〉も意外と一定数見られるということにも気づいていらっしゃるかもしれません。
この2種類の“ミス”は、いずれも、「の」と意味・用法が近い中国語の“的”が背景にある可能性が高いと思われます。そこで、中国語の“的”にも簡単に触れつつ、中国語話者の学習者(以下、「学習者」)が「の」の使いすぎ/不足を減らしていくためのポイントを考えていきたいと思います。
- 書いた人:古賀 悠太郎(中国語話者のための日本語教育研究会)
- 台湾・静宜大学外国語学部日本語文学科准教授。専門は日本語学・日中言語対照研究。台湾での日本語教育歴は、現在9年目。
- 著作:『現代日本語の視点の研究―体系化と精緻化―』(ひつじ書房, 2018年)、「対話の場面で「太郎は嬉しい」が可能になるとき―人称制限はどのような場合にどの程度解除され得るか―」(『日本語文法』19巻1号, pp.20-36, 日本語文法学会, 2019年)